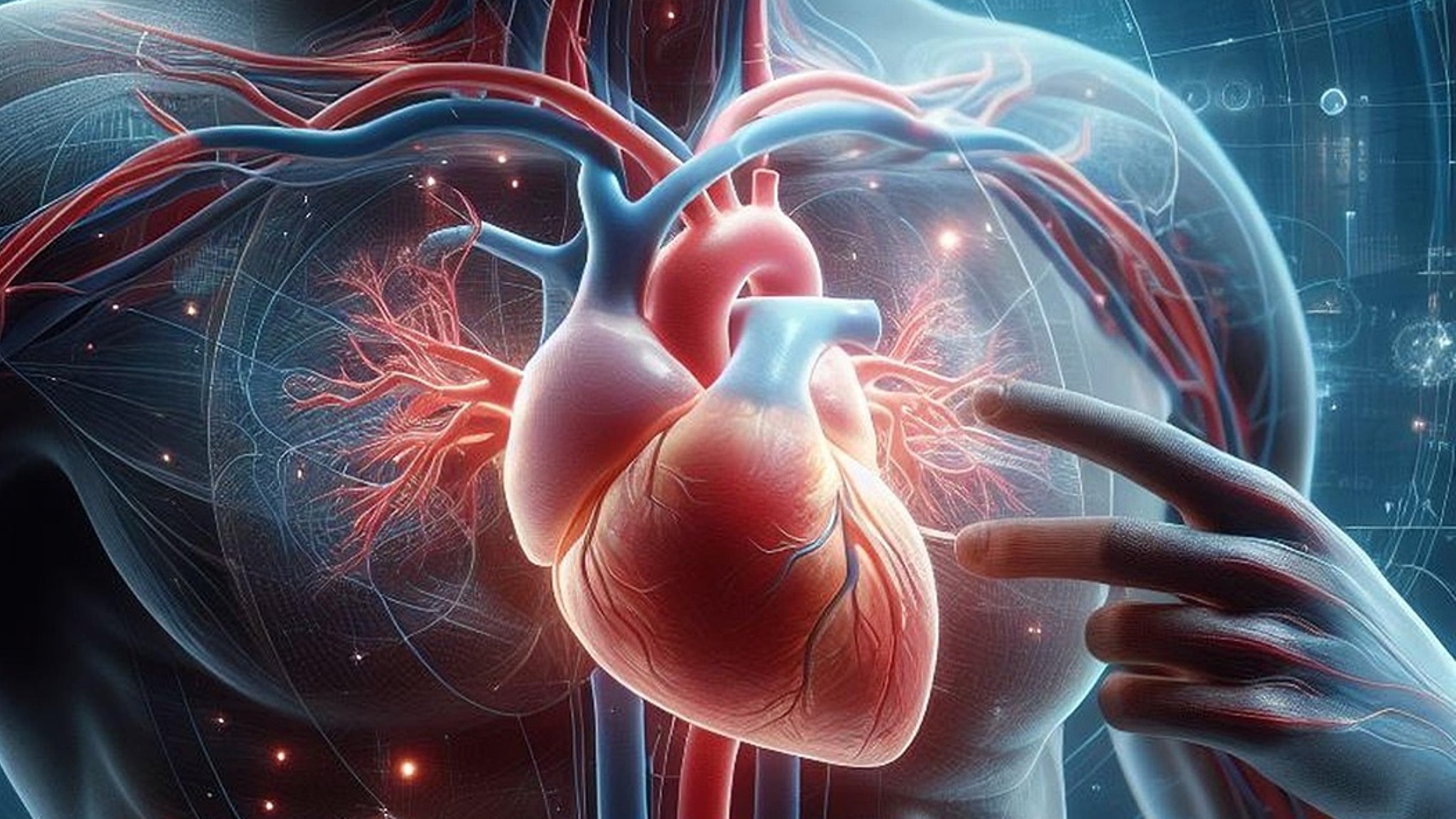PT・OT共通問題
第41回 問題13
心臓で正しいのはどれか。
1.右心室から肺静脈が出る。
2.冠状動脈は大動脈から分岐する。
3.大動脈弁は2尖である。
4.僧帽弁は3尖である。
5.卵円窩は心室中隔にある。
+ 解説
解答:2
解説
1.右心室からは肺動脈が出ます。肺静脈は左心房に開口する血管です。
2.冠状動脈は上行大動脈の起始部から分岐します。
3.大動脈弁は3枚のポケット状の半月弁です。
4.僧帽弁(左房室弁)は2尖弁です。
5.卵円窩は心房中隔(右心房面)に存在します。卵円窩は胎児期の卵円孔の痕跡です。
第43回 問題12
正しいのはどれか。2つ選べ。
1.成人の心臓は約500gである。
2.心軸は左前下方から右後上方に向かう。
3.房室弁は二尖弁である。
4.心臓壁は3層からなる。
5.刺激伝導路と呼ばれる交感神経が存在しる。
+ 解説
解答:2・4
1.心臓の重量はおよそ200-300gです。
2.心底から心尖に向かう心臓の長軸を心軸といいます。心軸は右上後方から左下前方に向かって斜走します。
3.右房室弁は三尖弁、左房室弁(僧帽弁)は二尖弁です。
4.心臓壁は内層から心内膜・心筋層・心外膜の3層構造になっています。
5.刺激伝導系は特殊心筋線維で構成されています。
第44回 問題13
心臓の刺激伝導系について正しいのはどれか。2つ選べ。
1.左脚と右脚は房室束へ興奮を伝える。
2.洞房結節はペースメーカーと呼ばれる。
3.房室結節は上大静脈口のすぐ右側に位置する。
4.房室系は洞房結節と房室束からなる。
5.プルキンエ線維は心室壁に放散している。
+ 解説
解答:2・5
1.刺激伝導系は洞房結節→房室結節→房室束(ヒス束)→左脚・右脚→プルキンエ線維の順に伝達します。
2.洞房結節は興奮の発信地でペースメーカーと呼ばれています。
3.房室結節は右心房後壁で冠状静脈口の直上に位置します。房室結節は洞房結節よりも太く、密な特殊心筋線維で構成されています。
4.房室系は房室結節とヒス束からなります。
5.プルキンエ線維は心室壁に放散しています。
第45回 午前65
心臓で正しいのはどれか。
1.心筋の収縮は主に水素イオンの細胞内流入によって生ずる。
2.通常、心筋は伸張されると収縮力が低下する。
3.ノルアドレナリンは心筋収縮力を増加する。
4.左心室と左心房とは同時に収縮が始まる。
5.収縮期に冠血管の血流は増加する。
+ 解説
解答:3
解説
1.心筋の収縮は細胞内にカルシウムイオンが流入することにより生じます。
2.心室内の血液量が増大すると心筋(心室筋)は伸張され、その反動で収縮力が強くなります。これをフランク・スターリング(Frank-Starling)の法則といいます。心筋(心室筋)の収縮力が増大すると1回拍出量も増大します。
3.ノルアドレナリンは交感神経の末端から分泌される神経伝達物質です。交感神経が優位に作用すると、心拍数は増加し心筋の収縮力は高まります。
4.心房と心室の間には線維輪があり心房の興奮は直接心室に伝達されません。心房から心室への興奮は特殊心筋による刺激伝導系によって伝えられます。洞房結節→房室結節→ヒス束→左脚・右脚→プルキンエ線維の順に興奮は伝わります。房室結節から房室結節に興奮が伝わると同時に心房が収縮し、プルキンエ線維が心室を収縮させます。
5.冠血管の血流は心臓の収縮期に減少し、拡張期に増大します。
第45回 午後55
心臓で正しいのはどれか。
1.心臓壁は3層からなる。
2.大動脈弁は2尖弁である。
3.右心室から肺静脈が出る。
4.卵円窩は心室中隔にある。
5.健常成人の心臓は約500gである。
+ 解説
解答:1
解説
1.心臓壁は心内膜・心筋層・心外膜の3層構造です。
2.大動脈弁と肺動脈弁はポケット状の3枚の半月弁です。左房室弁(僧帽弁)は2尖弁です。
3.右心室からは肺動脈が出る。肺動脈は左心房に開口する。
4.卵円窩は心房中隔の右心房面にあるくぼみである。
5.心臓の重量はおよそ200-300gである。
第46回 午前56
心臓の解剖学で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.僧帽弁は3尖弁である。
2.大静脈は左心房に入る。
3.右心室から肺動脈が出る。
4.卵円窩は心室中隔にある。
5.冠状動脈は大動脈から分岐する。
+ 解説
解答:3・5
解説
1.僧帽弁(左房室弁)は2尖弁です。
2.右心房には上大静脈・下大静脈・冠状静脈洞が開口します。左心房には左右の肺静脈が開口します。
4.卵円窩は心房中隔の右心房面にあるくぼみである。
5.冠状動脈は上行大動脈の起始部から分岐します。
第48回 午後57
刺激の伝わる方向で正しいのはどれか。
1.左脚→ヒス束
2.右脚→房室結節
3.洞房結節→房室結節
4.心室外膜側→心室内膜側
5.心室中隔右心室側→心室中隔左心室側
+ 解説
解答:3
解説
刺激伝導系は洞房結節→房室結節→房室束(ヒス束)→左脚・右脚→プルキンエ線維の順に伝達します。
第50 午前56
洞結節があるのはどれか。
1.右心房
2.右心室
3.左心房
4.頸動脈洞
5.冠状静脈洞
+ 解説
解答:1
解説
洞房結節は上大静脈の右心房への開口部に位置します。
/st-slidebox]
第54回 午後56
心臓で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.心臓壁は2層からなる。
2.右房室弁は三尖弁である。
3.心室中隔は左心室側に凸である。
4.心尖は第8肋骨間に位置する。
5.冠状動脈は大動脈から分岐する。
解答:2・5
解説
1.心室壁は心内膜・心筋層・心外膜の3層構造です。
3.心室中隔は右心室側に張り出した凸型構造をしています。
4.心尖は第5肋間隙に位置します。(心底は第2肋間隙に位置する)
第54回 午後63
心臓の刺激伝導系でないのはどれか。
1.固有心筋
2.洞房結節
3.Purkinje線維
4.房室結節
5.房室束
+ 解説
解答:1
解説
刺激伝導系は洞房結節・房室結節・房室束(ヒス束)・左脚・右脚・プルキンエ線維から構成される。心房や心室の心筋を固有心筋、刺激伝導系の筋を特殊心筋といいます。
第56 午前56
心臓について正しいのはどれか。
1.僧帽弁は三尖弁である。
2.冠静脈洞は右心房に開口する。
3.大動脈弁には腱索が付着する。
4.冠動脈は大動脈弓から分岐する。
5.右冠動脈は前下行枝と回旋枝に分かれる。
+ 解説
解答:2
解説
1.僧帽弁(左房室弁)は2尖弁です。
3.心室にある円錐状に突出する乳頭筋と房室弁を結ぶヒモ状の組織を腱索といいます。
4.冠状動脈は上行大動脈から起始部から分岐します。
5.右冠状動脈は後室間枝になる。左冠状動脈は前室間枝(前下行枝)と回旋枝に分枝します。
第56回 午前65
心臓について正しいのはどれか。
1.冠動脈の血流は収縮期に増加する。
2.左心房と左心室は同時に収縮が始まる。
3.心筋は伸張されると収縮力が低下する。
4.心筋の収縮はH+の細胞内流入により生じる。
5.ノルアドレナリンは心筋収縮力を増加させる。
+ 解説
解答:5
解説
1.冠動脈の血流は心臓の拡張期(弛緩)に増加、収縮期に減少します。(体循環とは逆:対循環は収縮期に血流は増加、拡張期に減少する)
2.心臓の収縮は刺激伝導系によって興奮が伝わり起こります。洞房結節からの刺激により心房が収縮、プルキンエ線維の興奮により心室が収縮します。
3.心室内の血液量が増大すると心筋(心室筋)は伸張され、その反動で収縮力が強くなります。これをフランク・スターリング(Frank-Starling)の法則といいます。心筋(心室筋)の収縮力が増大すると1回拍出量も増大します。
4.心筋の収縮(第2相)は細胞内にカルシウムイオンが流入することにより生じます。
5.ノルアドレナリンは交感神経の末端から分泌される神経伝達物質です。交感神経が優位に作用すると、心拍数は増加し心筋の収縮力は高まります。
第56回 午後64
心筋について正しいのはどれか。
1.平滑筋である。
2.単収縮は生じない。
3.ギャップ結合はみられない。
4.静止張力は骨格筋よりも大きい。
5.活動電位持続時間は約5msecである。
+ 解説
解答:4
1.心筋には横紋があり、横紋筋に分類されます。
2.心筋は単収縮が生じます。心筋は脱分極後にカルシウムイオンが流入することで脱分極が長時間持続します(プラトー)。そのため活動電位の不応期は長く、加重や強縮は起こりません。
3.心筋はギャップ結合によって電気的・機能的に連絡しています。
4.心筋の静止張力は骨格筋よりも大きく、伸展すれば伸展するほど大きな張力を発生することができます(フランク・スターリングの法則)。
5.心筋(心室筋)の活動電位持続時間は約300ミリ秒です。骨格筋の活動電位持続時間は1-5ミリ秒です。
第57回 午前56
心臓について正しいのはどれか。2つ選べ。
1.右房室弁は三尖弁である。
2.冠静脈洞は左心房に開口する。
3.大動脈弁には腱索が付着する。
4.Valsalva洞は肺動脈の起始部に位置する。
5.左冠動脈は心室中隔前方2/3に血液を送る。
+ 解説
解答:1・5
解説
2.冠状動脈洞は右心房に開口します。
3.心室にある乳頭筋の先端と房室弁を結ぶヒモ状の組織を腱索といいます。
4.Valsalva洞は大動脈起始部の隆起部です。ここから左右の冠状動脈が分岐します。
第58回 午前64
心臓の刺激伝導系で正しいのはどれか。2つ選べ。
1.洞房結節は心室中隔にある。
2.房室結節の伝導速度はHis束より速い。
3.房室結節の興奮はHis束より先に生じる。
4.刺激伝導系の細胞は活動電位を生成できる。
5.洞房結節の活動電位持続時間はPurkinje 線維より長い。
+ 解説
解答:3・4
解説
1.洞房結節は上大静脈の右心房への開口部に位置します。
2.刺激伝導系の興奮伝導速度はHis束・Purkinje 線維は2-5m/秒、心房筋・心室筋は1m/秒、房室結節は3cm/秒です。
3.刺激伝導系の興奮は洞房結節→房室結節→His束→左脚・右脚→プルキンエ線維の順に伝わります。
4.刺激伝導系は自発的に一定のリズムで拍動することできます(心臓の自律性)。
5.洞房結節の活動電位持続時間は100-300ミリ秒、Purkinje 線維は300-500ミリ秒です。
第58回 午後55
心臓の構造で正しいのはどれか。
1.僧帽弁は3尖である。
2.大動脈弁は2尖である。
3.洞房結節は左心房にある。
4.卵円窩は心房中隔にある。
5.三尖弁は右心室の流出口にある。
+ 解説
解答:4
解説
1.僧帽弁(左房室弁)は2尖弁です。
2.大動脈弁は3枚のポケット状の半月弁です。
3.洞房結節は上大静脈の右心房への開口部に位置します。
5.右心室流出口の弁は肺動脈弁(3枚のポケット状の半月弁)です。三尖弁は右房室弁です。
国家試験対策動画